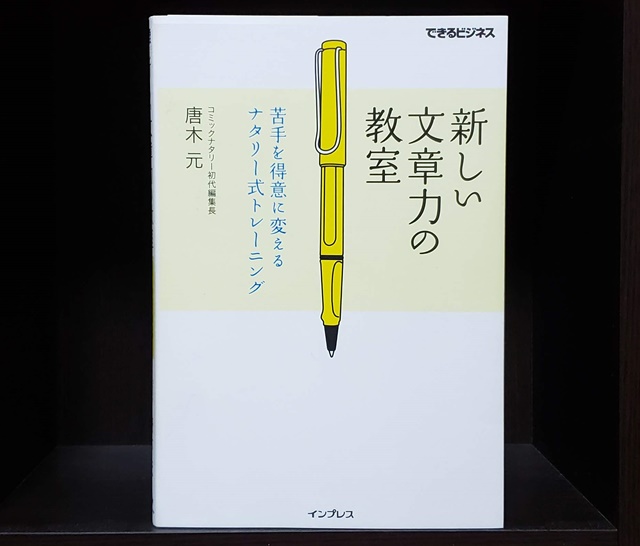文章の書き方を学べる本『新しい文章力の教室』の感想。
過去のじぶんに向け結論から言うと
絶対に読むべき一冊
です。
と目鱗でした。実践すれば効果も抜群。
こんな先入観がありましたが打ち消してくれました。
『新しい文章力の教室』は書けないという基礎的な悩みを気持ちよく解決できる本。
プラモデルのように作り方の手順が決まっていれば誰でもできるようになりますよね?
文章もコレと同じだと筆者は教えてくれています。
社会人はもちろん
中学生~高校生くらいの頃から、書かれているような文章術を学ばせるべき
くらいに今は思っています。
文章力系の本を読んだのは本書が初めてだったというのも大きいですがその点を割り引いても良書だと思います。
おすすめ。
もくじ
新しい文章力の教室とはどんな本?
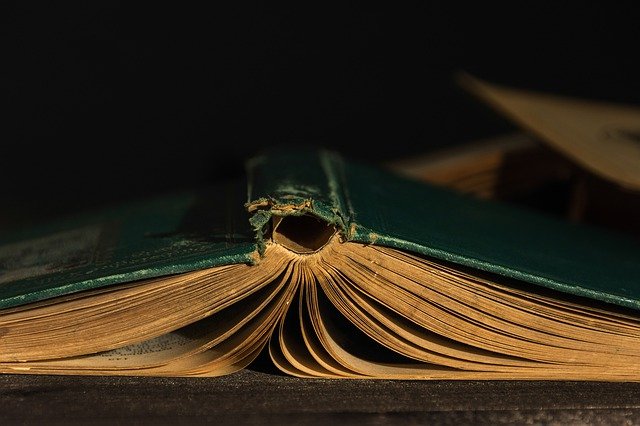
『新しい文章力の教室』は書けないという大きな悩みを細かく分解して、まるでプラモデルを組み立てるかのように、ロジカルに書けるようにしてくれる教科書のような本。
プラモを組み立てるように文章を書く方法やアイデアは学校や会社では誰も教えてくれません。
文書について学んでいない人が世の大半を占めているということです。
したがって本から学んだ内容をほんの少しでも実践するとすぐにでも効果を感じられます。
『新しい文章力の教室』では冒頭で
良い文章とは何か?
について以下のように明確にしています。
すごく明快で納得。
どれだけ素晴らしい内容だろうと最後まで読んでもらわなければ伝わりません。
完読されてこそ内容がどうだったかを評価してもらえます。
良い文章ってなんだろう?
とモヤっとしていたらどう考えるべきか解らない。
具体的な目標を設定しておくことによって視界がクリアになり目標を見失うことなく進んでいくことができます。
読み手に読む努力を押し付けるのではなく最後まで読んでもらうために書き手が努力する必要があるということです。
わたしはここを勘違いしていました。
少し大袈裟かもですがこの一節を覚えておくだけでも本を買った価値があると思います。
完読してもらうことが文書を書く目標。
じゃあ完読してもらうためにはどうするか?を考えて実践するのが書き手の努力。
この本はどういった人がターゲット?

ブログ、SNS、企画書、報告書、レポート等あらゆる文章を少しでも書く機会がある人が「新しい文章力の教室」のターゲット読者。
特に社会人はどのような職種でも日報を書いたり報告書を書いたりする機会は多々あると思います。
ちなみにわたしの仕事は生産設備のメンテナンスで、意外にも文章を書く機会は山ほどあります。※2021年時点
20歳のわたしからすると
設備のメンテナンスなんて文章を書く機会なんてないのでは?
と思うかもしれません。
ところがわたしの職場においては1件のメンテナンスをするごとに必ず文章付きで記録を残します。
大体平均で1日5件くらいで多い時は10件くらいは作業記録を書きます。
その他にも社内外のメールや各種報告書などわたしのような一般の作業員でも文章を書く機会がとても多い。
文章なんて関係ないわ~と思っている人にも、ぜひ一度手に取って欲しいです。
本の内容を実践したらどんな変化が起こったか

『新しい文章力の教室』の内容を実践して変化したこと
上記のような変化を3ヶ月から半年というかなり早い段階で感じています。
その①稟議書が一発で承認された
新しい文章力の教室を読み始めたタイミングでちょうど稟議書(りんぎしょ)を書く機会がありました。
稟議を起案するまでの流れは以下。
- 草案を書く
- 上司に確認してもらい、フィードバックを受ける
- 指摘箇所を修正する
- 起案!
①〜③を何度も繰り返し修正箇所が無くなるまでやりとりをします。
大体3回くらいは修正が入るのが常でした。
過去にも何度か稟議書を書いていましたが、これまでの文章力だと自分で書いた文章はほぼ残っておらず9割以上が上司の文章になるパターンばかり。
なんで、恥ずかしい話ですが
「これって自分が書く意味あるのかな・・・?」
といつも思っていました。
それくらい文章力が皆無だったわたしですが、本に書かれている内容を実践してみたところ稟議の文章はほぼ修正なしの一発OKをもらうことができました。
効果抜群でした。今までの自分はただ方法を知らなかっただけだったんです。
本を読んでから実践経験がまだまだ少ないのに早くも効果が出たのが驚き。
一発OKになったポイントは特に以下の3つを意識したおかげだと思います。
- いきなり書き始めない
- 書くためのパーツ(骨子)を揃える
- 文章の構造を考える
その②③文章を褒められるようになった
今までも下手なりにたくさん報告書を書いてきましたが文章を褒められたことはありませんでした。
ここ最近で報告書を書く機会が増えたのもあり本を読んだ後からはトレーニングのつもりで読みやすいように書く努力を続けていました。
そんなある時にひとつの報告書に対して直属の上司から
「この報告書すごくよく書けてるね。さすがだね。」
と、このように文章を褒めてもらえることができました。
「そんなことないっすよ〜」
と一応謙遜しておきましたが心の中ではガッツポーズ。
これまでは文章を褒められたことは誇張なしで無かったので素直に嬉しいです。
知識と実践の力は凄い。
実務として仕事が全然できなくても文章がそれなりに書けるとなんとなく仕事ができる人と錯覚されやすくなりそうだなと思いました。
それくらい文章力は大事です。
その④他人の文章が気になる
こんなことを言うと傲慢だと思うし、そんなお前はどんだけなんだとマジで思いますが一言。
みんな文章下手すぎぃ!
役職についている人やかなり上位の役職者の人でも1文1文がすごく冗長で何を言っているのか何が言いたいのかさっぱり分からない文章を書く人がたくさんいます。
文章に関心がなかった頃はそんなこと気にも留めないし他人の文章の良し悪しを測るレベルすら自分にはありませんでした。
しかし一度こうやって学んでみると大多数の人は今までのわたしと同じように文章について何も勉強していないことがわかります。
これまで難解かつ冗長な文章で何が言いたいのか分からない文章に出会ったときには
「自分の頭が悪いせいだ」
と思っていました。
だがしかし!
本当に頭が良い人は伝わるように書いてくれています。
何故なら伝わらなければ文章を書く意味がないからです。
まさに
良い文章とは、完読される文章である
ですね。
まとめ

『新しい文章力の教室』は
文章を勉強したことがないすべての人に読んで欲しい本です。
会社で文章を書く人がお互いに文章を学んでいれば認識の齟齬がグッと減って生産性がめちゃめちゃ上がるだろうなと思いました。
これまで文章はセンスだと思っていて ”国語や作文は苦手なんですぅ~” と避けていましたが、文章力は学んで実践すれば誰でも一定できることが分かりました。
折を見て読み返したい本です。
以上!
オススメの本